
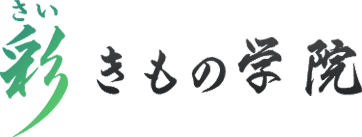

着付けをトータルに学ぶ方のための充実したコースです。自分がひとりで綺麗に着るために、半衿の付け方、補整の作り方から始めます。入門で学んだ技術に加えて、普段着から礼装まできものの着付け、帯結び、他の人に着付ける技術を習得します。
授業料は分割でお支払いいただけます。
入会金、年会費、維持費等はございません。
お支払い方法は、現金・郵便振込の場合、授業料は1,2,3回払い(大学は2回迄)、受験料・認定料は1回払いです。
クレジットカードの場合は、すべて 1 ~ 10 回払いです。分割手数料は、各カード会社指定の手数料に依ります。
万一、中途で受講できなくなったときは、全回数の半分以下の場合は半額返金、その後はお戻しできません。
但し、6ヶ月未満で再入学された場合は納入済みの授業料は有効です。
カードの解約は、ご本人が直接信販会社へご連絡下さい。

『 人生の楽しみと義母への感謝 』
茶道や華道をたしなんだ 今は亡き義母は、自分の着物を買う時には必ず私にも何かしらあつらえてくれました。その度に一枚また一枚と増え、ほとんど空だった私の和ダンスは、着物や帯で一杯になりました。
彩きもの学院と出会えたおかげで、それらの着物を活かした人生の楽しみを得ることができました。そして、私を娘のように大切に思ってくれた義母への感謝を深める機会になりました。 今年の春は、曲がりなりにも自分で着物を着て友人とお花見ができ、とてもうれしかったです。このうれしさを心の糧にして、着付けの上達に向けできる限りチャレンジを続けたいと考えています。

『 ここだ!! 』
五年程前に娘の成人式の振袖を購入したお店で着付け教室を勧められ、しばらく通っていました。教わっていくうちに、もっとしっかりと基礎から学びたい事と着物全般の知識を身につけたいと思うようになり、新たに教室を探し始めました。
着物販売がなく着付けに特化している彩きもの学院を見つけ「ここだ!!」と思いすぐに通い始めました。先生方は些細な質問でも丁寧にわかりやすく、さらにはプラスアルファの知識まで全力で教えて下さいます。クラスの仲間にも恵まれ、毎週有意義な時間を過ごしています。私の着物人生は始まったばかりですが、広く深く長く楽しんでいきたいと思っています。

『 初めての習い事 』
「 何で何も習わせてくれなかったの? 」成長してから母に何度も言った言葉です。この歳になって習い事を始めるきっかけとなったのは、綺麗なままタンスから出てきた祖母の着物を見て、これ着たい!自分で着れるようになりたい!よし!習いに行こう!となったからです。
今ではとても楽しく銀座校に通わせていただいており、 まだまだ下手ではあるものの、自分で着付けができるまでになりました。 何かを始めるのに早いも遅いもないのだということを実感しております。 これからもっと着物を楽しみたいので 、 先生方を見習い、努力しながら、でもやっぱり楽しみながら学んでいきたいと思います。

『 着物への憧れ 』
着物は日本文化を象徴する美しい衣裳ですが、最近では着る機会もなかなかなく日本人でありながら遠い憧れの存在になっていました。 これではいけないと振り絞って、彩きもの学院の門を叩きました(実際には電話をしただけですが…)
着付けやっぱり大変ですが、思っていた以上に面白いです。なかなか覚えられなくて悪戦苦闘の日々ですがいつか気軽に着られる日々を夢見て頑張っていきたいです。

『 私と着物 』
ある日、実家に帰ると着物が置いてありました。祖母が終活のためにタンスの整理をしたのです。その当時の私は長襦袢が何かもわからないほど無知でした。長い間、この家に暮らしていたのに一度も実家で着物を見たことがありませんでした。
長い間誰の目にも触れられず、着られることもない着物を見て、素敵と感じると同時に、もったいないと思いました。この着物を着て、再び着物が着物として活動し私の人生と共に歩めたら素敵だろうと思い、貴学院の入門コースに参加し、今に至っております。まだまだ着方は、思い通りにはできませんが、先生方の指導のもと、自分の思うような着方ができるように、これからも頑張りたいと思いますのでご指導よろしくお願いいたします。

『 美しい着姿を目指して 』
嫁入り時にあつらえてもらった着物を自分で着てみたいと、入門科に飛び込みました。初めは堅苦しいかしら、厳しいかしら・・・と不安もありましたが、先生方やスタッフの方々はとても優しい方ばかりで、毎週のお稽古の日が楽しくて待ち遠しいものになりました。
基礎科に進むと、下着から肌襦袢・長襦袢・着物・そして帯と着方のひとつひとつを細かく、丁寧に教えていただけます。先生のご指導のおかげで、自分なりに着物が着られた時は、子供の頃に浴衣を着て夏祭りに出かけた時のようなワクワクとドキドキの混じった気持ちで嬉しくなりました。これからもそのワクワク感を忘れずに、先生や先輩方の美しい着姿を目指して楽しく学んでいきたいと思っております。

『 目指せ、着物美人!! 』
子供の卒業式に母からもらった着物を着たい!!子供に袴を着せてあげたい!!と 思い入門コースに申し込みました。 入門の時には上手にできなかったことが、基礎科になると徐々にできるようになり、毎回楽しく受講をしています。先生方の着姿や、仕草がとても素敵で、いつか私も着物美人になりたいという目標ができ、有意義な時間を過ごせるようになりました。
これから色々な行事に参加させていただきながら、外出時のいろはを覚え、着物でたくさんお出かけしたいです。そして次は子供の成人式に、振袖を着せてあげられるようになりたい!!と新たな目標を見つけました。

着物に出会えた喜び
タンスの整理をしていたらレトロな紅葉柄の羽織が出てきました。この着物を着て美術館などに行くことができたらどんなに素敵かしらと思い着付けを学びたいと思いました。先生方の美しい着姿に心が華やぎ、授業では着物や帯の説明を受け、日本人の美的感覚の素晴らしさに感激しました。授業の他にも色々な行事に参加しています。
組紐講座では大好きなブルーで帯締めを組みました。大変でしたが大切に使っていこうと思います。9月にはユネスコ文化遺産の結城紬研修で糸を紡ぐ様子や絣の絵柄に合わせて織る繊細な工程に感動しました。
着物に出会い充実した日々を送ることができ感謝しています。

魔法の言葉
20年毎の自己革新。年代最後の年となる令和5年にそれは始まりました。「着物をまとう」という挑戦です。未知の世界に飛び込んで得る、驚きや感動はその後にも必ず繋がっていくと思っています。
動機はいたって単純。40年以上も眠らせてしまった着物を何とかしたい!そこで目にした貴学院の入門コースに即申し込みました。自信を持って自装ができるまでは続けようと決めて頑張ってこれました。
それは先生の魔法の言葉のおかげです。「そう、そう」「いいんじゃない」。回を重ねるにつれて自信と楽しみを感じました。学院で得た感動や自信がどこへどのようにつながっていくのかに思いを巡らす今日この頃です。

基礎科の認定試験を終えて
「着物を自分で着てお出かけしてみたい!」と思い立ち、入門科に飛び込んでから早一年。先日基礎科の試験を終えました。全く何もわからない状態からのスタートで当初は着付け認定試験が黒留袖の自装と聞いた時は自分に出来るのだろうかと不安でした。
しかし先生のご指導のもと、必死の練習を重ね、試験当日、何とか着ることが出来た事は感激を覚えるとともに一つの自信になりました。 先生方の丁寧で熱心なご指導のお陰で自分なりに少しずつ着実に上達できているという実感と喜びを感じております。先生や先輩方の素敵な着姿を目指して、これからも沢山の事を楽しみながら吸収していきたいと思っております。
着物を通して
母の残した一枚の着物。何十年の時を経てもなお存在感のある伝統のものを子や孫にも伝え継いで行きたいと思い、まず自分が着物を知ることからとの思いで貴学院に入りました。戸惑いながらも、徐々に着物の世界が見えるようになり、初めて自分で着られた時は嬉しく格別の思いがしました。
先生方の自然に醸し出される、落ち着きと所作の美しさを拝見し、着物を着ることで、改めて自分の立ち居振る舞いや内面に目を向けることの大切さを実感させられました。長い間継がれてきた日本の伝統や美意識、また謙虚に自分は控え相手を思いやる心など日本人として誇るべき気質までも着物を通して再認識し考えさせられた一年でした。継なげていきたいと思います。

着付けのお手伝いをしたい
娘の大学の卒業式に私も着物で出席しました。帰りの電車で帯が解けてしまい困っていた時に、隣に立っていた方が、雨で濡れていた車内の床に膝を付きながら解けた帯を直してくれました。どんなに助かったことか。そんな風に困っている人を助ける事が出来るようになりたい思い、彩きもの学院に通い始めました。
クラスの雰囲気も良く毎回楽しい時間を過ごす事が出来ています。また、毎回見させて頂く先生方の季節ごとの着こなしと素敵なコーディネートの着物姿はとても魅力的で、いつか私も先生方のような着こなしが出来るようになりたいと、もうひとつの新たな目標となっています。
『持ち物』については、以下のものは括弧内のもの全てを含めたものを指します。