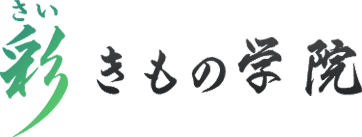
授業料は分割でお支払いいただけます。
入会金、年会費、維持費等はございません。
お支払い方法は、現金・郵便振込の場合、授業料は1,2,3回払い(大学は2回迄)、受験料・認定料は1回払いです。
クレジットカードの場合は、すべて 1 ~ 10 回払いです。分割手数料は、各カード会社指定の手数料に依ります。
万一、中途で受講できなくなったときは、全回数の半分以下の場合は半額返金、その後はお戻しできません。
但し、6ヶ月未満で再入学された場合は納入済みの授業料は有効です。
カードの解約は、ご本人が直接信販会社へご連絡下さい。

『 チャレンジして良かったインターン制度 』
研究科に進級したばかりで、技術も自信もまだまだ不足している私ですが、それでも何とか自分で着物を着られるようになってきた、ということに喜びを感じていました。そんな折、インターン制度のご案内に興味を持ちチャレンジ精神で飛び込みました。実際に始めてみると、自分の稽古の時とは異なる視点から着付けの再確認や気づきがありとても楽しいです。
また、教室には着物を着ていくことが必須のため、毎回大汗をかきながら着付けていますが、それ自体も大変勉強になっています。インターン生としての経験は、私にとって着物をさらに身近なものにしてくれました。今ではチャレンジして本当に良かったと心から思っています。

『 着物へのおもい 』
満開のチューリップを見ながら私は一人で着物を着て有楽町朝日ホールへ向かいました。そう、認定式です。 私の着物の記憶をたどると、子供の頃は、お正月には晴着を、お盆には浴衣を、大人になってからは雷門へお出かけしたり、姉のお茶会、友人の結婚式等に着せてもらっていました。
結婚後は家業が忙しく仕事をするだけの毎日でしたが休職する事になった時、ふと新聞広告が目に入り、「着物を着てみよう!」と思いお教室に通い始めました。高齢の私には戸惑う日々でしたが、先生に繰り返しお教えて頂き、この日を迎えることができ感謝しています。 今後はできるだけ多く着物を着てお出かけしたいと思っています。

『 着物ライフを楽しもう 』
ふと目にした新聞の広告、それは彩きもの学院入門クラスの案内でした。着物好きだった祖母が母に誂えた着物がつまった和箪笥を実家から持ってきたものの、途方に暮れていたところの広告。思い切って申し込みました。
入門クラス・基礎科を経て研究科のクラスが始まったばかりですが、鎌倉へ初めての お出かけ会(あいにくの雨でしたが)新年会、認定式、入門クラスへのインターン生の経験は憧れつつも近寄り難い世界が少し近づいたように感じました。何より自分で着物を 着られることがこんなに楽しいこととは思いませんでした。先生方からのアドバイス、先輩方、スタッフの皆様との交流を支えに、引き続き修了を目指して頑張りたいと思います。

『 着て楽しむ、着せて学ぶ 』
これまで着物は特別な日の正装として着付けていただくものでした。入門科に始まり基礎科、 研究科と先生方の丁寧なご指導のおかげで、今では一人で着物を着て外出できるまでになりました。教室では新しい友人にも恵まれ、着物でお出かけする楽しい時間も過ごしています。
美しく魅せるための見えない部分への配慮など、 着崩れしないための工夫、苦しくない着付けなど学びがたくさんあり、レッスンのたびに着付けの奥深さを感じます。そして一番は学院の技術がなす衿元の美しさです。 衿が決まると着姿に自信が持てます。和装をする方には是非味わっていただきたいです。 今は小学生の娘に、近い将来振袖を着付けたい!を目標に学んでいきたいと思います。

『 楽しい世界発見 』
着物好きだった母の着物を着たいと思い立ち、入学いたしました。 着物を作る度に「これ新しいのよ」と見せてくれた嬉しそうな母の顔。 まだまだ未熟ですが、一人で着物が着れるようになり、そんなことを思い出す機会も増えました。
教室では着付け技術とともに着物の柄、格、季節に合わせたコーディネートなどの知識も教えていただけるので興味深く、わくわくするひと時です。研究科の実技試験は 振袖の他装と伺って今から緊張しているのですが、19歳で結婚して成人式はミセスの装いだったのでほんのちょっぴり嬉しさも。これまでほぼ仕事優先の世界にいましたが、 着物を通じて新しい世界が広がりました。

『 卒業のお祝いに 』
母が茶道の先生をしている影響で着物は割と身近な存在で、着る機会も少なからずありましたが、正直あまり興味がありませんでした。そんな母が新調してくれたり、仕立て直してくれた着物が気づけばタンスから溢れ出るくらいに…。このままにしておくのはもったいないと思い、着付けを習うことにしました。
何の知識もなく、なかなか上達せず、仕事も忙しくなり、途中で挫折してしまいそうになりましたが、先生方や2人のクラスの相方さんの励ましのおかげで続けることができました。娘の大学の卒業式に袴を着付けてあげることができたことで、とても自信がつきました。自装も他装もそつなくこなせるように頑張りたいと思っています。
『持ち物』については、以下のものは括弧内のもの全てを含めたものを指します。