
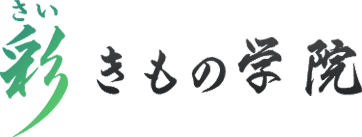

着物の着付けには、多くのアイテムや小物が必要です。ネット上でも着物に必要なアイテムの情報は多数存在しますが、初めて着物を着る場合、「何を揃えればよいのか」「どの順番で使うのか」と迷う方も多いはずです。
そこでこの記事では、着物を着る際に必要な道具や小物について、それぞれの名称と役割を一つひとつ分かりやすく解説します。事前に揃えて準備することで、美しい着姿に仕上げられるので、ぜひ参考にしてみてください。
着物を着る際には、着物本体に加えて下着類、帯周りのアイテムが必要です。また、体型に合わせて補正用品を用意したり、一人でも着付けをしやすい便利アイテムを活用したりすることで、美しい着姿を整えられます。必須ではありませんが、髪飾りやバッグなどの小物も添えると、全体の印象がいっそう華やかになるので、あらかじめ用意しておくとよいです。
着物本体に必要なものは以下の通りです。

日本の伝統衣装である着物は、着姿に欠かせないメインアイテムです。結婚式・お茶会・観劇など、それぞれのシーンにふさわしい着物の種類があるため、着用する場所や目的を考えて選びましょう。自分の体型や好みの色柄を見つけることで、着物をより楽しめます。

着物の下に重ねて着る長襦袢は、大切な着物を直接肌に触れさせないための下着です。汗や皮脂から着物を守るだけでなく、防寒の役割も果たします。通常の一枚タイプのほか、上下が分かれた二部式、上半身だけの半襦袢など、着やすさを重視した種類も増えています。
長襦袢の首元に縫い付けて使う半衿は、汚れ防止とおしゃれの両方の機能を持つアイテムです。化粧や汗で汚れやすい衿元を保護するため、こまめに取り替えて洗濯します。
基本は白色ですが、刺繍入りなどもあり、成人式などの華やかな場面では装飾性の高い半衿が選ばれています。
ここでは、着付けに必要な小物について解説します。

幅の広い帯状の伊達締めは、着物の形を保つためのアイテムです。使い方は、長襦袢を着た後に1本、着物を着た後に1本、合計2本使って固定します。最近では、マジックテープで留められるタイプが人気で、初めての方でも簡単に使えます。

腰紐は、着物の丈を調整したり、着崩れを防いだりするために使うアイテムです。一般的には5〜6本程度用意しておけば安心ですが、着付けの方法や体型によって必要な本数は異なります。美容院などで着付けをお願いする場合は、事前に何本必要かを確認しておくとよいです。
衿芯は、衿元をピンと美しく見せるために、半衿の中に入れて使うアイテムです。衿芯があることで、衿の形が綺麗に決まり、品のある着姿を演出できます。材質はプラスチックや紙などさまざまで、硬さや厚みも選べます。注意点として、一度折り目をつけると衿に跡が残るため、保管する際は折らずに丸めて収納するのがコツです。暑い季節には風通しのよいメッシュタイプも便利です。
帯板は、帯を巻いたときに前面がシワにならないよう、帯の内側に差し込んで使うアイテムです。帯板を入れることで、帯の表面が滑らかに整い、すっきりとした印象の帯姿になります。種類には板タイプとベルト付きタイプがあり、礼装用には大きめのサイズ、カジュアル用には小ぶりなサイズを用いるのが一般的です。
帯枕は、お太鼓結びの美しい立体感を作り出すために使うアイテムです。背中側の帯の膨らみを支える土台となり、紐で固定するタイプやガーゼで包まれたタイプがあります。サイズは仕上がりの好みに合わせて選べ、ボリュームのあるお太鼓にしたいなら大きめを、控えめにしたいなら小さめを選びます。
コーリンベルトは、衿元の開きを防ぐために使うアイテムです。両端にクリップが付いたゴムベルトで、着物や長襦袢の衿をしっかりと固定できます。必須ではありませんが、多くの着付け教室や美容院で利用されています。
マジックベルトは、マジックテープで固定するタイプの伊達締めです。従来の紐を結ぶ手間がなく、着脱が簡単なため、初めて着物を着る方にもおすすめです。ゴム部分は劣化することがあるため、定期的なチェックと交換が必要ですが、着付けをより手軽に行えます。
ここでは、着物の着付けに必要な帯について解説します。
帯は、着物の腰に巻いて固定する必須アイテムです。丸帯や袋帯などいくつかの種類があり、丸帯は留袖、袋帯は訪問着などのフォーマル着物、名古屋帯は小紋や紬、半幅帯は浴衣に合わせるのが基本です。
着物と帯の格を揃えることがマナーとされており、組み合わせ次第で全体の印象が大きく変わります。
帯揚げは、帯枕を隠して帯姿を整えるための布です。見える部分はわずかですが、色や柄の選び方によって着物全体の雰囲気を大きく変えられます。素材も綸子や縮緬など種類が豊富で、さりげなく季節感を演出することも可能です。
帯締めは、帯の中央を横切るように結んで固定する紐です。帯がほどけないようにしっかり押さえる役割と、装飾として華やかさを添える役割を兼ね備えています。礼装には金銀をあしらった組紐、普段着にはカジュアルな丸ぐけが一般的で、丸い形状の丸組や平たい平組など、さまざまな種類があります。
ここでは、着物の下着・肌着として必要なものについて解説します。
和装ブラジャーは、胸の凹凸を抑えて着物に適したシルエットを作るための専用下着です。必須ではありませんが、より綺麗な着姿を目指す方には着用をおすすめします。胸のサイズが大きい方は、さらしなどで補正を加えることもあります。
肌襦袢は、素肌の上に直接着用する和装用の下着です。汗を吸収して長襦袢や着物を汚れから守るアイテムで、一体型のタイプやセパレートタイプなど種類が豊富です。基本的にはどの着物にも共通して使えるため、長く愛用できる着心地のよいものを選びましょう。
裾除けは、下半身用の肌着として使われるアイテムです。素肌に直接身につけ、汗の吸収や防寒、さらに着物の裾さばきを良くする役割を果たします。形状は、腰巻タイプ、パンツタイプ、スカート型のほかに、肌襦袢と一体化したスリップタイプもあります。形状によって機能性が異なるので、着物を着る場面や季節に応じて使い分けるとよいです。
着物の下に履くステテコは、汗を吸収して着物への汗染みを防ぎ、足さばきを良くして歩きやすさを高めるためのアイテムです。必須アイテムではありませんが、下半身のまとわりつきを防げるので、歩く機会が多い日には着用をおすすめします。
足袋は、和装時に履く靴下のことです。草履の鼻緒に合わせて親指と他の指が分かれた独特の形状をしています。礼装には白足袋が基本ですが、カジュアルな着物には色柄付きの足袋を選んで楽しむこともできます。サイズが合わないと足が痛くなったり見た目が悪くなったりするため、自分の足に合ったものを選ぶことが大切です。
ここでは、着物の着付けに必要な補正用品について解説します。
ウエストのくびれや腰のくぼみ、胸元などをフラットに整えるためのアイテムです。選ぶ際は薄手のフェイスタオルがおすすめで、新品である必要はありません。色柄も着物に隠れて見えないため、無地にこだわらなくても問題ないです。補正用タオルは、基本的に5~6枚程度用意しておけば、一通りの着付けに対応できます。
補正パッドは、タオルの代わりに使える着姿を綺麗に見せるための専用アイテムです。形が整っているため初心者でも使いやすく、毎回同じ仕上がりが期待できます。ただし、着付け師によってはタオルの方が使い慣れている場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。
晒は胸元の補正に使うアイテムで、胸が大きい方の補正道具として昔から使われています。肌着として汗を吸収して着物の汚れを防ぐほか、体の凹凸をなだらかに整える役割もあり、使用することでより美しい着姿に仕上げられます。
ガーゼは、脱脂綿やタオルを固定するために使用します。一般的には、長くロール状のものを使い、胴回りに3周半程度巻ける長さ(5メートル程度)があれば十分です。
和装用の晒ガーゼは地厚で伸縮性が少ないため、締め付けが気になる方はドラッグストアで買える一般的なガーゼがおすすめです。以前使用したガーゼが残っている場合は、使用済みでも問題なく使えます。
脱脂綿は、タオルでカバーしきれない細かい部分に入れて補正するために使用します。振袖の着付け一回分なら50グラムもあれば十分ですが、着付け師によって使い方が異なるため、自分では切らずにそのまま持参するとよいです。
脱脂綿は使い回せますが、体に直接触れるため、色が変わっていたりゴミが付いていたりする場合は新しく用意しましょう。
ここでは、着物を着る際に用意しておくとよい装飾品について解説します。
草履は、着物に合わせて履く伝統的な履物です。草履には高さがあり、フォーマルなシーンではかかとが5〜6cmと高めのものを、カジュアルな着物には3〜5cm程度のものを選ぶのがおすすめです。
下駄は、浴衣に合わせる履物です。草履に比べてカジュアルに用いられ、木製の台に鼻緒がついた形状をしています。種類には二枚歯や右近下駄など種類があり、履き慣れていない方は歩きやすい右近下駄を選ぶとよいです。
重ね衿は、着物の衿元に重ねて使う装飾アイテムです。伊達衿とも呼ばれ、着物を何枚も重ね着しているように見せる効果があります。わずか数センチしか見えませんが、衿元に華やかさや奥行きを出してくれます。最近では、簡単に取り付けられるクリップ式の重ね衿もあり、色や柄を組み合わせて衿元のアレンジを楽しむことができます。
帯留めは帯締めの中央に通して使う装飾品です。素材は金属製、陶器製、ガラス製などさまざまで、デザインも花や季節のモチーフなど豊富に揃っています。帯元に華やかさを添えられますが、フォーマルなシーンでは帯留めを使用しないので、着物の格やTPOに合わせて使い分けましょう。
着物用のバッグは、草履とセットになっているケースも多いです。個別で揃える場合は、フォーマルなシーンには金や銀などの高級感があるもの、振袖や袴には華やかな柄のものを選ぶとよいです。着物用のバッグは小ぶりで収納力が限られているため、荷物が多いときはサブバッグを用意しましょう。
髪飾り・かんざしは、ヘアスタイルを華やかに見せる装飾品です。パールをあしらった髪飾りや水引、花のモチーフなどさまざまなデザインがあり、好みに合わせて選べます。どの髪飾りを選べばよいか分からない場合は、着物の色や柄と合わせると統一感が生まれ、上品に仕上がります。
扇子は、涼をとるための実用性だけでなく、写真撮影の際の小道具としても活用できます。扇子の柄や装飾には意味があるので、フォーマルなシーンでは金銀をあしらった格式高いものを、カジュアルなシーンでは季節の絵柄が描かれたものを選ぶとよいでしょう。扇子は帯に挟んで持ち歩けますが、礼装の場面では扇子の使用にも作法があるため、格式を重んじる場では事前に確認しておくと安心です。
羽織は、着物の上に重ねて羽織るアウターです。カジュアルな着物の場合、羽織に特別な作法はなく、好みに合わせて自由に楽しめますが、フォーマルなシーンでは羽織を着用しないのが一般的です。
着物用ショールは、寒い季節に使える防寒アイテムです。フェイクファーやベルベット、ウール、カシミヤなど幅広い種類があり、着物の雰囲気に合わせて選べます。ただし、室内ではショールを外すのがマナーとされています。
ここでは、着物の着付けをサポートする便利グッズをご紹介します。
着物クリップは、着付けのときに仮固定として用いるアイテムです。着物クリップで衿元や袖を一時的に留めると両手が自由に使えるので、自分で着物を着るときに用意しておくと便利です。洗濯バサミで代用する方もいますが、着物に跡が残ったり傷めたりする恐れがあるため、専用のクリップを使いましょう。
和装用ハンガーは、着物を保管したり陰干ししたりするときに使う専用のハンガーです。洋服用のハンガーとは異なり、着物の袖を広げて掛けられる構造になっており、着物の形を崩さず、シワを防ぎながら保管できます。
衣装敷は、着物を広げたり畳んだりするときに下に敷く紙です。床の汚れやほこりなどから着物を守る役割があり、自分で着付けをするときの着替えスペースとしても使えます。
着物の着付けに最低限必要なものは以下の通りです。
| 着物(きもの) 長襦袢(ながじゅばん) 半衿(はんえり) 伊達締め(だてじめ) 腰紐(こしひも) 帯(おび) 帯板(おびいた) 帯枕(おびまくら) 帯揚げ(おびあげ) 帯締め(おびじめ) 足袋(たび) 肌襦袢(はだじゅばん) 裾除け(すそよけ) |
今回は、着物の着付けに必要なアイテムや装飾品についてお伝えしました。
着物を美しく着るためには、着物本体だけでなく、下着や補正用品、帯周りの小物、装飾品、便利グッズまで一式揃えることが大切です。
用途やシーンに応じてアイテムを選ぶと、快適で華やかな着姿を作れるので、自分らしい着こなしを楽しめます。
着付けを依頼する場合でも、着付け師によって必要なアイテムや使い方が異なるので、事前に確認した上で必要なものをしっかり揃え、着物の楽しさや美しさを存分に引き出しましょう。。SNS映えも狙えるので、自分らしい着こなしとおでかけプランを考えながら楽しんでみてくださいね。
❖彩きもの学院では新規生徒募集を行っております。
詳しくは下記リンク先まで!
❖ 関連項目
・-トップページに戻る―・