
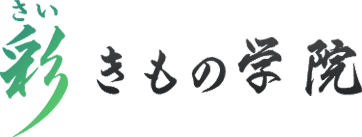

ポール・ヴェルレーヌ【1844-1896】の「落葉」は「フランス抒情詩の最高水準をゆくもの」と称えられている詩で、日本では上田敏【1847-1916】の名訳により高校教科書にも掲載、人口に膾炙しました。旧暦で九月といえば秋到来ですが、昨今、旧暦の名残は微塵も無く、残暑というには長すぎる夏が続きます。歳時記は年中行事や季節の推移、俳句の季語など中心の暦で、九月は晩秋、旧暦は月の満ち欠けに基づき、ひと月が28日でで四年に一度、閏(うるう)年を設けた太陰暦で明治までの暦。歳時記や旧暦はもはや影が薄くなりましたが、心だけは「芸術の秋」を意識したいもの。
電気の無い時代、夜の灯りは「月」で、空を見上げるだけで日付や時刻も知りえたとか。秋の夜長、月を見上げ、心に浮かぶ思いを「絵画、音楽、文学」にこめた古人の心情を時空を超えて受け止めてゆきたいものです。。
目次
長月(ながつき) 空が特に澄み渡り、長い時間、月を眺められることから。
関東大震災を教訓とし、防災意識を高めるために1960年に制定。
富山市八尾町で開催の300年以上の歴史を持つ伝統的な祭。哀調のある胡弓の調べ、越中おわら節の哀切な旋律にのって、無言の踊り手達が練り歩く。歴史ある街並みと相まって、時代を超えた幻想的な世界へ誘ってくれる。二百十日の大雨をおさめ、五穀豊饒を願う秋の風物詩。。
夜中に大気が冷え、草花や木に朝露が宿りはじめる頃。降りた露は光り 白い粒のように見え「露が降りると晴れ」と言われ、朝霧はその日の天気を伝えてくれる。
五節句の一つ。陰陽説で最高の数字・九が重なる最高の節句。「菊」は邪気を払う力があると菊酒を飲み、菊の花を飾り、菊香を移した綿で身体を拭う(着せ綿)の風習がある。平安時代に「菊の宴」が催され、時を経て、秋の園遊会に。
父の観阿弥とともに猿楽を能楽として大成し「初心忘るべからず」などの名言
含む『風姿花伝』などの日本最古の芸論書を残した世阿弥【1363?-1443?】の忌日。能は観世流として現代に受け継がれている。足利義満の庇護の下、当時の貴族・武家社会が尊ぶ幽玄の好みに合わせ「言葉、所作、歌舞、物語」に幽玄美を漂わせる[夢幻能]を大成させた。代表作に『高砂』『井筒』『実盛』など50曲近くあり、現在も能舞台で上演されている。
約7万4千人が犠牲に。平和記念像は神の愛と仏の慈悲を象徴し右手は原爆の脅威、左手は平和、横の足は投下直後の長崎の静けさ、縦の足は 救った命 閉じた目はは戦争犠牲者の冥福を祈っている。
【アメリカ】2001年に発生した同時多発テロ事件の犠牲者を追悼する日。米史上最悪のテロ事件とされ、約3,000人の犠牲者を追悼する様々な行事が行われる。
平均寿命は、男性が81.歳、女性が87.歳。女性は40年連続で世界の一。一方で健康寿命「自立した生活ができる期間」は、男性と女性で15年の差がある。。
俳人・歌人・正岡子規《1867~1902》の忌日。松山藩士・正岡家の長男として伊予国温泉郡で生誕、長じて東京帝大国文科に在籍、同級生や友人に夏目漱石、海軍軍人の秋山真之、菌類学の南方熊楠等。吐血しても鳴き続けるホトトギスを自分に重ね、俳誌「ホトトギス」を創刊、俳号「子規」はホトトギスの漢字表記。俳句、短歌、評論、随筆などの創作活動をし「歌よみに与ふる書」で江戸時代までの形式的な和歌を否定、改革を促した。最も有名な句に「柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺」現存する都文化史蹟「子規庵」では、糸瓜忌特別展示「戦後80年 戦災を乗り越えた遺品達」を展示、公開日は不定期の為,、下調べを。
彼岸はあの世とこの世が最も近い日とされ、主にお墓参りをする。
彼岸の中日 国民の祝日。
旅愁
詞 犬童球渓
作詞の犬童が故郷の熊本県人吉への郷愁を綴った詩で、明治40年発表の『中等教育唱歌集』に採用された秋の名曲。林芙美子の「放浪記」の冒頭「私は北九州の或る小学校で、こんな歌を習った事があった。更けゆく秋の夜旅の空の侘しき…なつかし父母、私は宿命的に放浪者である。私は古里を持たない。」に引用。「放浪記」は演劇賞に名前を冠する菊田一夫【1908-1973】の脚本・演出で舞台化、1961年の初演から森光子【1920-2012】が亡くなるまで務め、上演回数は2000回を超えた。
ふけゆく秋の夜 旅の空の
わびしき思いにひとり悩む
恋しやふるさと なつかし父母
夢路にたどるは さとの家路 窓うつ嵐に 夢もやぶれ
はるけきかなたに心まよう
恋しやふるさと なつかし父母
思いに浮かぶは 杜のこずえ
・-トップページに戻る―・